プロペシア(フィナステリド)0.2mgと1mgの使い分けは?
最終更新日: 2022年08月31日 (水)

このコラムを読むのに必要な時間は約 8 分です。
最後まで有意義なページになっていますので是非ご覧ください。
INDEX
代表的な男性型脱毛症(AGA)治療薬であるプロペシア(一般名:フィナステリド)には、0.2mgと1mgという2つの剤形が存在します。
単純に考えると、0.2mgよりも1mgの方が5倍用量が多く、効果も5倍になるような気もします。
しかし、実際にはそんなことはなく、薄毛をしっかりと治療するためには、「最適な用量を見つける」ことが重要になります。
そこで今回は、プロペシアの効果や注意点、用量の使い分けなどに関して解説します。
プロペシア0.2mgと1mgの使い分けは?
プロペシアは、0.2mgから開始して1mgまで増量することができる医薬品です。
これだけ見ると、0.2mgよりも1mgの方が効果的なように感じますが、実際にはそうではありません。
フィナステリド(1 mg/日,0.2 mg/日)を用いた、414 名の「日本人」男性被験者を対象とした観察期間 48 週間の研究をおこなったところ、「1 mg/日では58%が軽度改善以上の効果」があり、「0.2 mg/日では 54%が軽度改善以上の効果」があったと報告されています。
1年間の継続投与を行なったところ、1mgで58%の人に効果があったのに対し、0.2mgでも54%の人に効果が出ています。
このように、用量を5倍(0.2mg→1mg)にすれば結果が5倍になるわけではなく、人によって必要な用量は違うということになります。
プロペシアを効果的に使用していくためには、「一人ひとりにあった最適な用量を見つける」ことがとても重要になります。
AGA治療を行う際には、自分自身で判断をせず、専門家の下で科学的根拠に則った治療を行うようにしましょう。
参考論文)Kawashima M, Hayashi N, Igarashi A, et al: Finasteride in the treatment of Japanese men with male pattern hairloss, Eur J Dermatol, 2004; 14: 247―254.
プロペシアの用法用量
プロペシアの用法用量としては、「フィナステリドとして0.2mgを1日1回経口投与する。なお、必要に応じて適宜増量できるが、1日1mgを上限とする。」と規定されています。
プロペシア錠にも、0.2mgと1mgという2つの剤形が存在しているため、これらの剤形を使い分けて、一人ひとりに最適な用量を見つけていくことになります。
そもそもプロペシア(フィナステリド)とは?
AGA治療の最もスタンダードな治療薬といえるのが「プロペシア」です。
プロペシア(一般名:フィナステリド)は、AGAの原因となる男性ホルモンを阻害する働きを持っており、薄毛の進行抑制効果が期待できます。
プロペシアの薬理作用

AGAの詳細なメカニズムとしては、テストステロンとよばれる男性ホルモンが、より強力な作用を持つ「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変化し、このジヒドロテストステロンが作用することで、結果的に薄毛の進行を促進させることが分かっています。
つまり、ジヒドロテストステロンをブロックする効果を持つ医薬品を使用することができれば、薄毛の進行を抑制することができるということになります。
プロペシアは、テストステロンをジヒドロテストステロンに変換する酵素(II 型5-α 還元酵素)を阻害することで、ジヒドロテストステロンの合成を阻害し、薄毛の進行を抑制することができると考えられています。
このように、プロペシアは、酵素の働きを阻害することで、ジヒドロテストステロンの生合成を抑制し、結果的に薄毛の進行を止めるという薬理作用を持つ医薬品です。
プロペシアの効能効果
プロペシアの効能効果は、「男性における男性型脱毛症の進行遅延」とされているように、あくまでも「薄毛の進行を抑える」というのが目的です。
薄毛の進行を抑えることで、新たに生えてくる髪が増加し、最終的には「増毛や育毛効果」が期待できるという作用になります。
そのため、プロペシアの治療を開始してすぐに髪が生えてくるというものではありませんのでご注意下さい。
女性のAGAに対しての効果
また、「女性の薄毛」として、女性型脱毛症(FPHL)や女性男性型脱毛症(FAGA)などが注目されるようになっています。
女性型の脱毛症であっても、その原因には男性ホルモンが関与している場合も多く、AGA治療薬が女性の薄毛治療に使用されることもあります。
しかし、プロペシアは、臨床試験(研究)において、女性への効果が認められなかったことから、女性に対して使用することはできません。
それだけではなく、妊婦への投与によって、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼす恐れもあり、妊婦または妊娠している可能性のある女性、授乳中の女性への投与は禁忌となっています。
インターネットなどで、プロペシアなどのAGA治療薬を個人が手に入れることができるようになっていますが、使用方法を間違えると取り返しのつかないことになる可能性がありますので、AGA治療を行う際には、必ず専門家にご相談下さい。
プロペシアの副作用
プロペシアの副作用として、「性欲減退」が1〜5%の方に確認されているほか、勃起機能障害や射精障害、精液量の減少などの男性機能障害が報告されています。
これらの副作用が日常生活や生活の質に影響を及ぼす可能性もありますので、注意が必要です。
また、過敏症や消化器症状が出現する可能性がある他、プロペシアは肝臓で代謝されるため、肝機能に影響を及ぼす可能性もあります。
プロペシア使用時には、特にこれらの副作用の出現に注意しながら、継続的にフォローアップしていく必要があります。
プロペシアの前立腺に対する影響は?
プロペシアなどのAGA治療薬に関しては、前立腺への影響などが不安視されていることがあります。
プロペシアは前立腺への影響を調べた研究が行われており、「前立腺癌のマーカーであ
る血清 PSA 濃度が約 50%低下する」ことが示されています。
前立腺がんの指標である腫瘍マーカーが低下するということは喜ばしいことのように感じますが、これは決して良いことばかりではありません。
プロペシアによって見かけ上の数値が低くなるということは、「本当のガンが見過ごされてしまう可能性がある」ということになります。
実際にはマーカーの値が高いのに、プロペシアを飲んでいるから、見かけの検査結果の数値が低く見えてしまう可能性があるということです。
そのため、プロペシアによるAGA治療中の方が医療機関に受診される際には、必ずプロペシアを内服している旨を報告するようにしましょう。
受診時だけではなく、健康診断や人間ドックなどでも、プロペシア内服を正しく伝える必要があります。
参考論文)D’Amico AV, Roehrborn CG: Effect of 1 mg/day finasteride on concentrations of serum prostate-specific antigen in men with androgenetic alopecia: a randomised controlled trial, Lancet Oncol, 2007; 8: 21―25.
AGA治療治療のガイドラインとは?
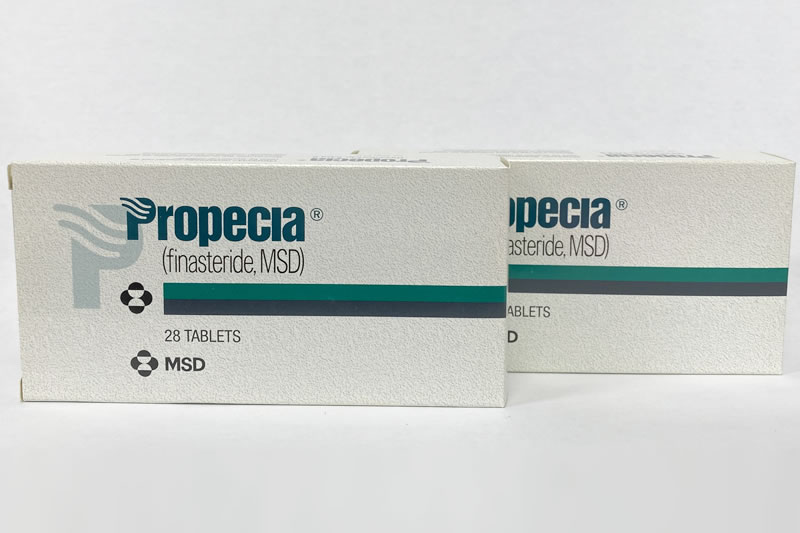
AGA治療におけるプロペシアの使用方法を理解するためには、「AGA治療治療のガイドライン」を参照するのがおすすめです。
ガイドラインとは、医師が疾患を治療する際の指針のようなものであり、基本的にはこのガイドラインに沿って治療が行われることになります。
それぞれのAGA治療薬の特徴や注意点、医薬品の使い分けなども記されていますので、プロペシアの詳しい使い方が知りたいという方は、「AGA治療のガイドライン」を読んでみると良いでしょう。
とはいえ、ガイドラインは医師向けに書かれているため、「読むのがとても難しい」というデメリットがあります。
「難しくて複雑なガイドラインを、誰にでも分かりやすく解説する」ということも医師の使命のひとつですので、AGA治療について詳しく知りたいという方は、お気軽に共立美容外科までご相談下さい。
共立美容外科では、カウンセリングや問診を無料で行なっているのはもちろん、オンライン診療なども実施しておりますので、必ずお役に立てると考えています。
参考)男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版/日本皮膚科学会
プロペシア(フィナステリド)は正しく使用しましょう
プロペシアは、AGA治療には欠かせない医薬品のひとつです。
効果と安全性のバランスが良く、多くの人がプロペシアで満足度の高い治療を受けています。
しかし、プロペシアは非常に有名になっていることから、インターネット上には様々な情報が飛び交っており、一部誤った情報が発信されていることも事実です。
「早く薄毛を治したい」という気持ちから、自己判断で1mgの高用量製品を使用するという方もいらっしゃいます。
しかし、プロペシアは、高用量を使用すればそれだけ効果も高くなるというわけではなく、一人ひとりに最適な用量というものが存在します。
用量をオーバーしてしまうと、効果が上手く発現できないばかりか、副作用ばかりが出てしまうというトラブルを招くことにもなります。
プロペシアだけではなく、AGA治療を行う際には、必ず専門医を受診するようにしましょう。
共立美容外科は、AGA治療にも力を入れており、様々な治療方法や施術をご提供可能です。
薄毛にお悩みの方は、まずはお気軽に共立美容外科までご相談下さい。
カウンセリングや施術のご相談など、
お気軽にお問い合わせください!
このページの監修・執筆医師








