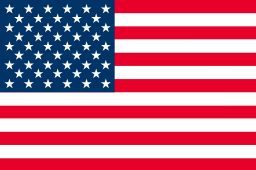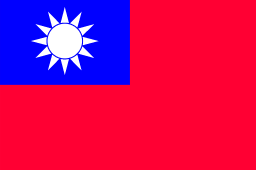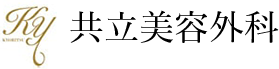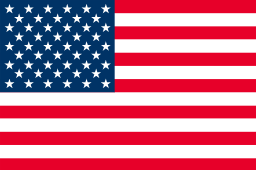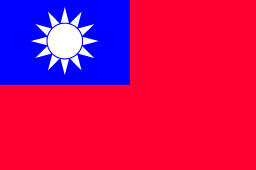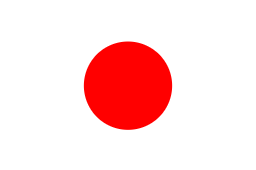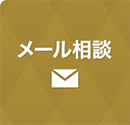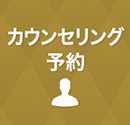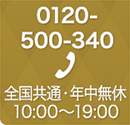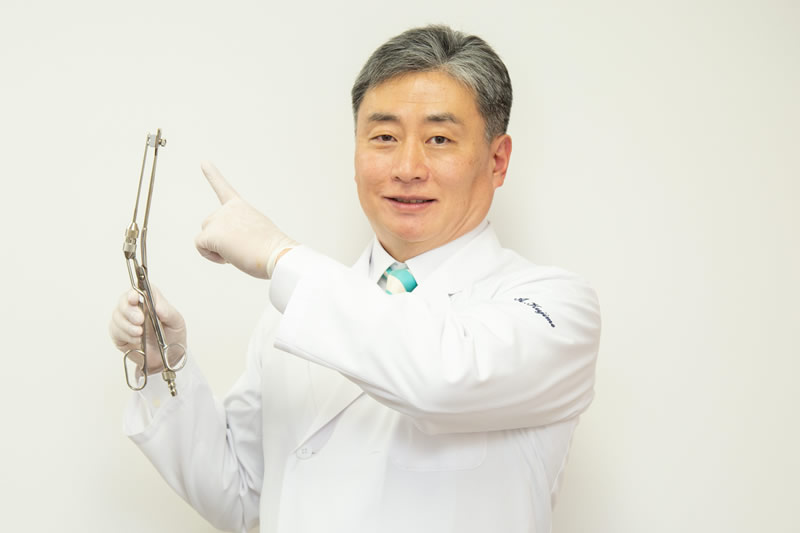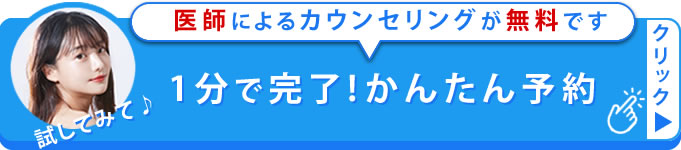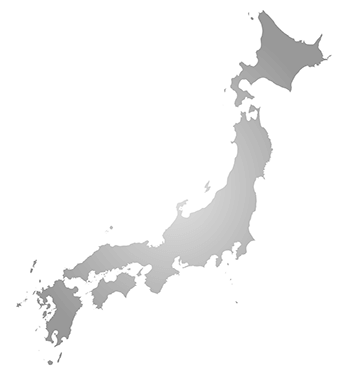日本美容外科医師会認定医院 | 相談・施術の流れ|美容整形・美容外科なら共立美容外科・歯科 ドクターひとりひとりが日々、技術の向上に努力しています。
Kyoritsu Biyo Scrap(KBS)
冬だけど脇汗が気になる?原因と対策方法を美容外科医が解説
公開日:2022年05月14日(土)
わきが・多汗症

このコラムを読むのに必要な時間は約 14 分です。
最後まで有意義なページになっていますので是非ご覧ください。
目次
脇汗と聞くと夏のイメージがありますが、ニオイのきつい冬の脇汗にお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
気温が低い冬は厚着をしますが、電車内や建物内は暖房が効いていて汗をかくシーンは意外と多いものです。
今回は冬の脇汗の原因や対策方法などについてご紹介します。
冬の脇汗は夏よりもニオイが気になる?
夏場はしっかりと脇汗対策をしていても、冬は特に何もしていないという方は多いかもしれません。
春夏の暖かい季節だけではなく、秋冬の時期にも意外と汗をかいているもの。
個人差はありますが、どんな気温でも人間は1日1リットル近くの汗をかいていると言われています。
よくある脇汗に関するお悩みとして「多汗」「ニオイ」「シミ・黄ばみ」の3つが挙げられますが、中でも冬の脇汗は夏よりもニオイが気になる傾向があるのです。
そもそも脇汗の独特なニオイ、「ワキガ」はなぜ発生するのでしょうか。
私たちの体には汗を分泌する汗腺があり、「エクリン汗腺」と「アポクリン汗腺」の2種類に分かれています。
このうちアポクリン汗腺から分泌される汗がワキガの原因となるのです。
ワキガはすべての人に起こるわけではなく、生まれつきアポクリン汗腺の数が多い人に起こります。
冬の脇汗がひどくなる原因
冬の脇汗について、
- 冬なのに空調の温度が高くて脇汗が出る
- 脇汗のニオイが周りに漂っていないか心配
- 脇汗のシミで衣服に黄ばみができていないか心配
といったお悩みを抱えた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
脇汗のお悩みはデリケートな問題であるため、周りの人に相談できずにどうしたら良いかわからないという方もいらっしゃるようです。
ここでは、冬の脇汗がひどくなる原因についてご紹介します。
一つひとつしっかり確認し、ご自身に当てはまるものがあれば改善していきましょう。
冬は代謝が高くなりやすい
そもそも基礎代謝とは、体温維持や心臓の動き、呼吸など人間が生きていくために最低限必要なエネルギーのこと。
何もしなくても消費されるエネルギーで、1日に消費するエネルギーのうち、約70%を占めています。
気温が10度以下になると、寒さから内臓を守ろうと私たちの体は体温を維持しようとします。
平熱を保つために熱を作り出してカロリーを消費するため、基礎代謝が上がるのです。つまり、気温が下がりやすい冬ほど私たちの体の代謝は高くなります。
しかし、代謝が高くなるのと同時に気になってくるのが脇汗です。
階段の昇降や歩行など少しの動作であっても脇汗をかきやすい状態になります。
ストレスや睡眠不足
人間の体には無数の神経があり、中でも内臓の働きなどを調整しているのが「自律神経」です。
自律神経は昼間や活動しているときに活発になる「交感神経」と、夜間やリラックスしているときに活発になる「副交感神経」の2種類があります。
2種類の神経がどのように作用するのかによって、心と体の調子は変化するもの。
何らかの要因によって神経のバランスが崩れると、心身に支障をきたし、ストレスや睡眠不足によって脇汗の量が増えると言われているのです。
脇汗のほかにも全身のだるさ、頭痛、肩こり、手足のしびれ、動悸、めまいなどの症状が表れることもあります。
ストレスによって脇汗が増えたと感じたときは、早めの受診をおすすめします。
ホルモンバランスの乱れ
女性ホルモンには「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」の2つがあります。
エストロゲンは乳房の発育や丸みのある体を作り、コラーゲンの生産を保ったり、自律神経の安定や子宮内膜を厚くして妊娠に備えたりする働きがあるのに対して、プロゲステロンは体温を高めたり食欲を増進させたりし、妊娠しやすい状態にする働きがあるのです。
ホルモンバランスは加齢やストレス、生理周期や不規則な生活リズムなどによって乱れやすいといった特徴があります。ホルモンバランスの乱れを放置すると、前項でもご紹介したように、自律神経のバランスも乱れ、脇汗だけではなく全身の不調にもつながってしまうのです。
このような事態を防ぐためにも、ホルモンバランスを整えることは大切です。
内臓脂肪や皮下脂肪が多い
人間は日常生活中の活動によって体内で熱を生み出し、体外に放出することで平熱を保っています。
しかし、内臓脂肪や皮下脂肪が多いと体温が上がりやすくなり、体温を下げる手段としてより多くの汗をかくようになってしまうのです。
内臓脂肪や皮下脂肪が多い人は肥満状態になっている傾向があります。
肥満者は運動習慣がない場合が多く、少し動いただけでも汗を大量にかいてしまうことも。
これは一定の運動量に対する酸素摂取能力が著しく低いことが関係しているのです。
酸素の摂取量が少ないと、無酸素下の「解糖系」という方法で運動エネルギーを得ようとします。
この方法で運動エネルギーを得ると、汗の中の乳酸が増加し、ニオイが強くなってしまうのです。
汗腺の機能が低下しやすい
夏は汗をかく頻度が高く汗腺の機能が高いため、汗に含まれているアンモニアやミネラルを血液に再吸収させて、水のような汗が出やすいです。
一方で冬は汗をかく頻度が低くなるため、汗腺の機能が低下します。
汗腺の機能が低下した状態で汗をかくと本来血液に取り込まれるはずのアンモニアなどがうまく吸収されず、汗に含まれるナトリウムの量が2倍になると言われています。
冬服は体温がこもりやすい
冬服はフランネルやポリエステル、ウールなど保温性や保湿性に優れた素材が多い特徴があります。
これらの素材を着ることで寒い冬を暖かく過ごせる一方で、脇汗をかきやすくなることも。
冬服はニットやセーター、コートなど毎日洗えないものが多く、汗のついた服に雑菌が繁殖してニオイが発生しやすい傾向があります。
ワキガかも? すぐに試したいセルフチェック
ワキガの診断には明確な基準がないため、自分ではなかなかわかりにくいものです。
ワキガは体質や生活習慣が影響している可能性が大きいと言われています。
下記のリストでいくつ当てはまるか確認してみましょう。
体質
- 両親、もしくは片親がワキガ
- 耳垢が湿っている
- 体毛が濃い
- 脇汗が多い
- 下着やシャツを着ると脇の部分が黄ばむ
- 腋毛に白い粉がついていることがある
生活習慣
- ストレスを感じやすい
- 汗をかく習慣がない
- 肉料理や揚げ物を食べる機会が多い
- たばこを吸っている
- 食事制限による過激なダイエットを行っている
いかがでしたか。
上記の内容はいずれも脇のニオイが強くなりやすい人の特徴です。
特に体質欄で複数個チェックが当てはまった場合はワキガ体質の傾向があります。
女性の場合、生理や妊娠、出産の際に一時的にワキガのニオイが強くなることも。
こうした女性特有の体の変化は女性ホルモンのバランスによって起こりますが、ワキガの原因となるアポクリン汗腺もこの影響を受けるのです。
更年期以降になると女性ホルモンの分泌量が減少するため、ワキガのニオイが気にならなくなることもあります。
冬の脇汗の対策方法
前項でご紹介したように、冬の脇汗はさまざまな要因から夏よりもニオイが強くなりやすい傾向があるのです。
冬の脇汗対策として、
- インナーを見直す
- 脱ぎ着しやすい服で体温調整する
- 入浴時に体のゴシゴシ洗いを避ける
- 制汗剤を使う
- 脇汗パットを使う
- 動物性脂肪の摂取頻度を抑える
- 汗をかく習慣を作る
7つが挙げられます。それぞれの対策方法について詳しく見ていきましょう。
インナーを見直す
冬は寒さ対策のためにヒートインナーを着用されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、ヒートインナーの多くは吸湿発熱素材になっているため、暑くなりすぎることがあります。
吸湿発熱素材とはレーヨンやポリエステル、アクリルなどの化学繊維を合成して作られたもので、体から発散された汗や湿気を吸収して発熱する仕組みになっているのです。
しかし、ヒートインナーの吸収量には限界があり、たくさん汗をかいた場合、吸収しきれなかった汗が蒸れてしまうことも。
この状態になると、汗のニオイが気になりやすくなってしまいます。
そこでおすすめなのが、冬用のインナーを見直すということ。
冬用のインナーとしておすすめの素材が、コットンです。
コットンは吸湿性が高く、温度調整に優れているという特徴があります。
肌ざわりも良いため、乾燥で敏感になっている肌でも安心して着用できるでしょう。
脱ぎ着しやすい服で体温調整する
冬はニットやパーカーなどのボリューム系衣類を着る機会が多くなります。
しかし、冬の汗は夏の汗よりもニオイが強いことに加え、その汗が衣類に付着しやすいといったことも。
冬の脇汗対策としておすすめなのが、脱ぎ着しやすい服で体温調整をすること。
「いつも歩いているうちに暑くなる」という方は、着込むのをやめておくのがおすすめ。
冬は電車や建物の中に入ると強い暖房によって汗をかくこともあります。
寒くなったらさっと羽織れるように、カーディガンなどを常に携帯すると良いでしょう。
外出中に汗をかいてしまったら、デオドラントシートなのでさっと素早く拭き取るように心がけてください。
入浴時に体のゴシゴシ洗いを避ける
「汗のニオイが気になって入浴時にゴシゴシ体を洗っている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
体をゴシゴシ洗うことによって、かえってニオイを増長させてしまっている可能性があります。
冒頭でもご紹介したように、汗腺にはエクリン汗腺とアポクリン汗腺の2種類があり、エクリン汗腺から分泌される汗は99%水分のためニオイがありません。
しかし、アポクリン汗腺から分泌される汗はアンモニア、ピルビン酸、たんぱく質などを含んでいる上、塩分がほとんど含まれないため、皮膚上に存在する常在菌がそれらを取り込んでニオイが発生してしまうのです。
通常であればアポクリン汗腺から分泌される汗は「表皮ブドウ球菌」の働きによってニオイが消えます。
しかし、ゴシゴシと体を洗うと表皮ブドウ球菌の個体数が減る代わりに、悪臭を放つ菌が増え、ニオイがさらに強くなってしまうのです。
体のニオイが気になるときはゴシゴシ洗いを避けるほか、使用する石鹸にも注意が必要です。
体臭を抑えたいときは殺菌効果と消臭効果を兼ね備えた石鹸の使用をおすすめします。具体的な成分は以下の通りです。
殺菌効果のある成分
ミョウバン、イソプロピルメチルフェノール、塩化ベンザルコニウム
消臭効果のある成分
柿タンニン(柿渋エキス)、緑茶エキス、クロロフィル、炭
制汗剤を使う
デオドラントと制汗剤は同じものであると認識されがちですが、別物です。
デオドラントは雑菌の繁殖を防いで汗のニオイを抑えるものであるのに対して、制汗剤は発汗を一時的に抑えるもの。
最近はスプレー、シート、ロールオン、クリームなどさまざまな形状の商品が発売されているため、用途や好みに応じて好きなものを選べます。
従来の制汗剤は塩化アルミニウムを使用しており、皮膚へのダメージが大きかったり、使用感が悪かったりするといった問題がありました。
しかし現在販売されている制汗剤は「クロルヒドロキシアルミニウム」と呼ばれる皮膚に優しい成分を使用しており、自然な使用感を実現しています。
しかし、汗は体温調整する上で重要な役割を果たしています。
「汗が気になるから」といって全身に制汗剤を使用すると、体温調節をうまく行うことができなくなって熱中症を引き起こすリスクも。
このような事態を避けるため、制汗剤の使用は脇に留めるようにしましょう。
制汗剤を使用しても脇のニオイが強く残ってしまう場合は、後ほどご紹介する美容外科手術を視野に入れることをおすすめします。
脇用パットを使う
脇汗対策として既に使っている方もいらっしゃるかもしれませんが、「大切な洋服を汚したくない」「脇汗を人に見られたくない」というときは、脇用パットの使用がおすすめです。
脇用パットとは脇汗を吸水パットの裏がシール状になっているもので、衣類に直接貼り付けて使用することで、脇汗が衣類に付着するのを防止。デオドラント効果があるものもあるため、気になるワキガのニオイを抑える効果も期待できます。
脇用パットは大きく分けて「衣類に貼るタイプ」「直貼りタイプ」「繰り返し使えるタイプ」の3種類に分けられます。
まず衣類に貼るタイプはメジャーなタイプのもので、パットの接着剤が肌に直接つかないため、敏感肌の方でも安心して使用可能です。
薄いものが多いため、ポーチに入れて外出先で取り替えることもできます。
直貼りタイプは、脇に吸水性のあるテープを直接貼るというもの。
伸縮性があるため腕を動かしてもずれにくく、しっかりフィットする特長があります。
ノースリーブを着るときにも使える透明タイプのものもあるため、季節によって使い分けることも可能です。
繰り返し使えるタイプは、脇用パットがインナーに付属しているというもの。
ブラジャーやブラキャミソールに付属しているため、通常のインナーと同じ感覚で使うことができます。
洗濯するだけで繰り返し使用可能で、毎回パットを購入する必要がないため、経済的なのも嬉しいポイントです。
動物性脂肪の摂取頻度を抑える
動物性脂肪とは、動物に含まれる脂肪のことで私たちの身体活動の大きなエネルギー源になります。
肉類やラード、牛乳や卵、乳製品のほか、ケーキやアイスクリームなどバターや乳脂肪を多く含んだ西洋料理や洋菓子などに多く含まれている傾向があるのです。
動物性脂肪に多く含まれるたんぱく質は体内で分解されるとアンモニアや硫化水素など、強いニオイを持つ物質を発します。
これらの物質は体内で酸化すると脂肪酸となり、ニオイの原因になるのです。
そのため、もともとワキガ体質でない人であっても、動物性脂肪を日常的に摂取していると体臭が強くなる傾向があります。
ワキガを防ぐためには動物性脂肪の摂取を控え、栄養バランスの取れた食生活に切り替えることが求められます。
加えてアルカリ性食品を積極的に取り入れることで、より効果的にニオイを抑えることが可能に。
アルカリ性食品の一例として、大豆・そば・人参・トマト・海藻類・きのこ類などが挙げられます。
汗をかく習慣を作る
体内に老廃物がたまると、ワキガのニオイはさらに悪化します。
そのため、ワキガのニオイを避けるために汗をかかないようにしていると、汗に含まれる老廃物の濃度が高まるため、一層ニオイが強くなる傾向も。
そもそも汗は体温を一定に保つためのもので、ナトリウムやカリウムなどのミネラル成分のほか、ニオイの元になる成分が含まれていますが、血液中へと吸収されて無臭になります。
しかし、汗をかく頻度が減ると汗を作り出すエクリン汗腺がうまく機能しなくなり、正常な汗を作り出せなくなってしまうのです。
エクリン汗腺の機能を正常に戻すために効果的なのが、汗をかく習慣を作るということ。
体に適度な負荷がかかる有酸素運動はもちろん、サウナや入浴でも発汗を促せます。
運動が苦手という方は、まずは毎日湯船に浸かる習慣を作りましょう。
美容外科手術を受ける
今回ご紹介した冬の脇汗対策の中でも短期間で効果を得られるものが、美容外科手術です。
脇汗対策に効果的な美容外科手術として、
- 超音波+ローラークランプ法
- ミラドライ
- ボトックス注射
の3つが挙げられます。
いずれも体へのダメージが少なく、ダウンタイムも短いため、生活に支障をきたすことなく手術を受けることが可能です。
それぞれの手術について詳しく見ていきましょう。
超音波+ローラークランプ法
超音波+ローラークランプ法とは共立美容外科が開発した、ワキガ・多汗症手術です。
従来のワキガ・多汗症手術では、脇をメスで大きく切除し、エクリン汗腺やアポクリン汗腺を切除する方法が一般的でした。
この方法はワキガの原因となるアポクリン汗腺を大量に除去できるメリットがある一方で、脇に傷口ができやすく、体への負担が大きいといったデメリットも。
そこで共立美容外科では体への負担を抑えてワキガ・多汗症手術を行うことができる、「ローラークランプ」と呼ばれる医療器具を開発。
ローラークランプを使ったワキガ・多汗症手術は、皮膚をローラーで抑えながら吸引するため、皮膚にダメージを与えずに、ワキガワキガのニオイの原因となるアポクリン汗腺や、多汗症の原因となるエクリン汗腺をしっかりと除去できます。
また、傷跡を保護する「KBシース」を手術中に使用することで、吸引棒を使用する際に発生する皮膚との間の摩擦を防げます。
よって、摩擦から生じる皮膚表面へのダメージを防ぎ、傷跡が残らないようにすることができるのです。
術後のダウンタイムは1、2か月程度で、時間の経過とともに周辺組織と見分けがつかないほどなじんでいきます。
このページの監修・執筆医師
-
磯野 智崇(いその ともたか)
共立美容グループ 総括副院長
-
略歴
-
- 1995年
- 聖マリアンナ医科大学 卒業
- 1995年
- 聖マリアンナ医科大学形成外科 入局
- 1999年
- 東大宮総合病院整形・形成外科 入職
- 2002年
- 共立美容外科 入職
- 2009年
- 共立美容外科 浜松院院長就任
- 2020年
- 共立美容グループ 総括副院長就任
-
-
主な加盟団体
日本美容外科学会
日本美容外科学会認定専門医
-
SEARCHどのような美容整形をお探しですか?
- お顔の
美容整形 - ボディの
美容整形 - お肌の
美容整形 - その他の
美容整形
×
新宿・名古屋・大阪・福岡をはじめ
全国26院 共通ダイヤル
0120-500-340
あの久次米総括院長も診察♪
新宿本院 直通ダイヤル
0120-500-340
銀座院 直通ダイヤル
0120-560-340
渋谷院 直通ダイヤル
0120-340-428
池袋院 直通ダイヤル
0120-340-800
立川院 直通ダイヤル
0120-489-340
上野御徒町院 直通ダイヤル
0120-340-444