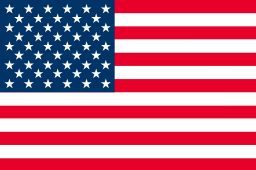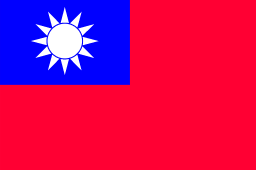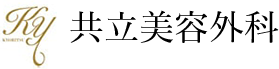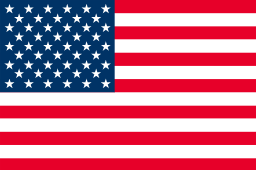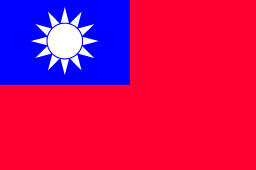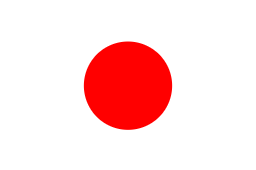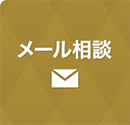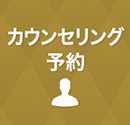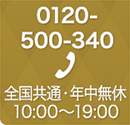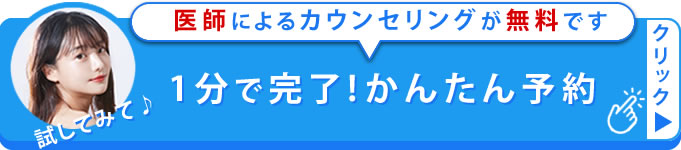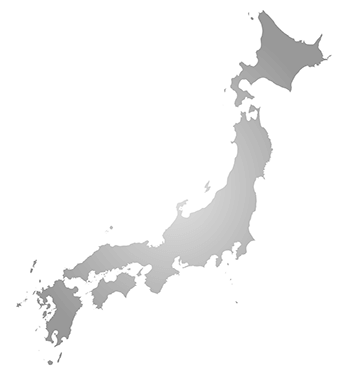日本美容外科医師会認定医院 | 相談・施術の流れ|美容整形・美容外科なら共立美容外科・歯科 ドクターひとりひとりが日々、技術の向上に努力しています。
Kyoritsu Biyo Scrap(KBS)
巻き肩は肩ボトックスで解消!巻き肩になる原因や日常的にできる改善方法などについても解説
公開日:2023年10月07日(土)
その他

このコラムを読むのに必要な時間は約 17 分です。
最後まで有意義なページになっていますので是非ご覧ください。
目次
巻き肩とは、肩が内側に入り込んだ状態のことです。長時間、パソコンやスマートフォンを使用している方は巻き肩になりやすいと言われています。巻き肩は見た目の印象が悪くなるだけでなく体の不調の原因にもなるため、早急に改善することが大切です。
そこで本記事では、巻き肩の原因や改善方法を紹介します。すぐにでも改善したい方におすすめの肩ボトックス(肩凝りボトックス)についても解説しているので、巻き肩にお悩みの方は参考にしてみてください。
巻き肩とは?
巻き肩とは肩が内側に丸まってしまうことで、両腕が体の前方に入り込んでいる状態のことです。本来であれば全身を横から見た時に耳の真下に位置する肩が前方に出てしまうため、正しい姿勢をキープできずに見た目が悪くなります。
また肩が内側に入り込むことで体の不調にもつながります。どのような不調が生じるかは後述しますが、巻き肩になってしまった場合は早めの対処が必要です。
巻き肩と猫背の関係性
先ほども紹介したとおり、巻き肩は肩が内側に入り込んだ状態のことです。左右の腕が前に出ることによって肩が内側に入り込みます。一方、猫背とは肩ではなく背中が丸くなった状態のことです。背骨に沿って体の縦ラインが丸くなっており、前傾姿勢になります。
巻き肩の方は猫背にもなっているケースが多いです。背中が丸くなって猫背になると、肩甲骨が外側に広がっていき脇の筋肉が硬くなります。肩甲骨を動かしにくくなり、巻き肩になりやすくなるのです。猫背と巻き肩を併発するとどちらもさらに治りにくくなってしまい悪循環に陥るでしょう。そのため猫背にならない習慣を身に付けることが重要です。
巻き肩になる原因
巻き肩になる原因は、主に以下のとおりです。
- 姿勢が悪い
- 筋力が低下している
それぞれの理由について詳しく解説します。
姿勢が悪い
姿勢が悪いと巻き肩になりやすくなります。例えば前傾姿勢が続くと、頭や首の位置が前にずれます。首が前にいくほど頭の重さで負荷がかかりやすくなり、バランスを取るために肩甲骨も前に突き出して巻き肩になってしまうのです。特にスマートフォンやパソコンを長時間使用する方は、無意識に背中が丸くなり姿勢が悪くなりやすいため注意しなければなりません。
また横向きに寝る習慣がある方も巻き肩になりやすいでしょう。横向きで寝転がると上半身に体重がかかり、その負荷を分散させようと肩が前に出やすくなり巻き肩になってしまいます。日中の姿勢だけではなく、寝るときの体勢にも気を付けるようにしましょう。
筋力が低下している
筋力が衰えていると、正しい姿勢をキープできずに巻き肩になりやすいです。そもそも正しい姿勢をキープするためには、主に以下に挙げる2つの筋肉が必要です。
- 背中の筋肉
- 胸の筋肉
背中の筋肉が衰えると、まっすぐな姿勢をキープできずに猫背になります。猫背になると肩甲骨を寄せたり胸を張ったりする胸の筋力も弱まり、巻き肩になりやすいのです。巻き肩を予防するには、この2つの筋肉をバランスよく鍛えることが大切です。
巻き肩になるとどのような不調が起こる?
巻き肩によって起こる主な不調は以下のとおりです。
- 肩や首がこる
- 頭痛が起こりやすい
- 睡眠の質が低下する
- 自律神経失調症につながる
- 頸椎ヘルニアになるケースもある
それぞれの不調について詳しく解説します。
肩や首がこる
巻き肩になると、肩や首がこりやすくなります。肩が内側に入り込むことによって肩と首を結ぶ筋肉が引っ張られるため、その筋肉に負荷がかかりやすくなり結果的に肩や首がこってしまうのです。
頭痛が起こりやすい
巻き肩になって肩が内側に入り込むと、血行不良によって頭痛が起こりやすくなります。そもそも血液は心臓から送り出されると、肩や首を通って脳へと送られる仕組みです。しかし巻き肩によって肩や首の筋肉が緊張状態にあると、血液が流れにくくなってしまいます。
また巻き肩によって体が縮こまってしまうと呼吸がしにくくなります。すると体内に取り込める酸素量が少なくなるため血液中の酸素濃度も低くなり、脳に必要な酸素を供給できなくなります。その結果、緊張型頭痛が起こりやすくなるでしょう。
睡眠の質が低下する
巻き肩になると、睡眠の質が低下する可能性があります。肩が内側に入り込むと、首の筋肉が硬くなってしまい副交感神経がうまく働かなくなります。副交感神経とは体がリラックスしているときに優位になる自律神経のことです。血圧や心拍数を下げたり、発汗を抑制したりする役割があり、質の良い睡眠を確保するためには副交感神経の働きが欠かせません。
しかし首の筋肉が硬直すると副交感神経の働きは鈍くなり、交感神経が優位になりやすいです。交感神経は副交感神経の反対の働きを持つ自律神経のことで、これが優位な状態であると体が興奮したままとなり、ぐっすりと眠れなくなる可能性があります。
自律神経失調症につながる
巻き肩になると肩凝りや頭痛といった体の不調を感じたり、睡眠の質が低下したりすることで結果的に自律神経失調症につながる可能性があります。不規則な生活習慣やストレスなどによって自律神経のバランスが崩れて、自律神経失調症になるとさまざまな不調が生じることも。具体的な不調の症状は以下のとおりです。
- 頭痛
- めまい
- 動悸
- 息切れ
- 手足のしびれ
- 倦怠感
- 食欲減退
- 睡眠障害
- 朝起きられない
- 記憶力や集中力の低下
他にもさまざまな不調が起こりやすく、場合によっては複数の症状が重なって現れることもあります。そのため、日頃から自律神経のバランスを乱さないように生活することが大切です。巻き肩を改善するのもその一つです。
頚椎ヘルニアになるケースも
巻き肩が長期化すると、首が前に出てしまってストレートネックになる可能性があります。ストレートネックとは、本来湾曲しているはずの首の骨が真っすぐな状態になってしまうことです。ストレートネックになると頭にかかる重力を和らげられなくなり、首や肩に大きな負荷がかかります。
また首の反りが強くなり頸椎や軟骨が圧迫されてしまうため、結果的に頸椎ヘルニアになってしまう可能性も否定できません。そのため巻き肩になった場合はすぐに対処することが大切です。
巻き肩のセルフチェック方法
巻き肩のセルフチェック方法は、以下の2種類があります。
- 立った状態でのセルフチェック
- 横になった状態でのセルフチェック
それぞれのチェック方法について詳しく解説していきます。
立った状態でのセルフチェック
立った状態で巻き肩かどうかを調べる方法は以下のとおりです。
- 全身をチェックできる鏡を用意する(用意できない場合は他の人にチェックしてもらう)
- 鏡に対して横向きに、リラックスした状態で立つ
- 2の状態をキープしたまま肩の位置を確認する
立った状態で肩の位置が耳よりも前に来ていれば、巻き肩と判断できるでしょう。また腕をだらんと垂らしたときに肘が体の外側に向いている場合や、手の甲が正面を向いている場合も巻き肩になっていると考えられます。
横になった状態でのセルフチェック
横になった状態でのセルフチェック方法は以下のとおりです。
- 床に仰向けに寝転ぶ
- 力を抜いてリラックスする
- 床と肩の間に隙間ができているかチェックする
床と肩の間に隙間ができていると肩が内側に入り込んでいる可能性があるため、巻き肩であると判断できます。肩に力が入っているとうまくチェックできないため、リラックスした状態で肩の位置を確認してみてください。
日常的にできる巻き肩の改善方法
自分で巻き肩を改善する方法もあります。日常的に行える巻き肩の改善方法は以下のとおりです。
- ストレッチをする
- トレーニングをする
- 正しい座り方を意識する
- 専用のアイテムを使用する
それぞれの改善方法を詳しくみていきましょう。
ストレッチをする
巻き肩を改善するためには、ストレッチを行うのが有効です。こり固まった筋肉を伸ばすことで、肩を正しい位置に戻しやすくなります。巻き肩の改善に役立つストレッチ方法をいくつか紹介します。これらのストレッチは毎日寝る前や休憩時間などに行ってみてください。
肩甲骨をほぐすストレッチ
肩甲骨をほぐすストレッチは以下のとおりです。
- 薬指や小指を肩に当てる
- 1の状態のまま肘で大きく円を書く
- 2を3~5回行う
- 反対側の肩も同様に回す
肩甲骨を正しい位置でキープするストレッチ
肩甲骨を正しい位置でキープするストレッチは以下のとおりです。
- 両手の甲を頭の上で合わせる
- 肘を曲げながら肩甲骨同士をくっつけるように腕をゆっくり下ろす
- 1~2を5回程度行う
肘先を伸ばすストレッチ
肘先を伸ばすストレッチは以下のとおりです。
- 足を軽く開いて立つ
- 右腕をまっすぐ前に出す
- 親指以外の指を左手で持つ
- 3の状態のまま、指を体側に引っ張りながら30秒キープする
- 2~4を反対側も同様に行う
- 右手の親指を左手で持つ
- 6の状態のまま、指を体側に引っ張りながら30秒キープする
- 6~7を反対側も同様に行う
トレーニングをする
巻き肩を解消するためには背筋や胸筋、腕周りのトレーニングが効果的です。これらの筋肉を鍛えることで、内側に入り込んだ肩を元の位置に戻しやすくなります。巻き肩の改善におすすめのトレーニング方法は以下のとおりです。
- 三角筋後部を鍛えるトレーニング
- 広背筋を鍛えるトレーニング
- 胸筋を鍛えるトレーニング
それぞれのトレーニング方法について詳しく解説します。
三角筋後部を鍛えるトレーニング
三角筋とは、腕の付け根にある筋肉のことです。三角筋後部を鍛えると巻き肩の改善につながります。三角筋後部を鍛えるトレーニング方法は以下のとおりです。
- 壁に背中を付ける
- 両腕を壁に密着させたまま、体との角度が80度くらいになるように横方向に広げる
- 手は壁に付けたまま、両腕の裏側で壁を押しながら背中を壁から離す
- 再び背中を壁に付ける
- 3~4の動作を5~10回、3~4セット行う
広背筋を鍛えるトレーニング
広背筋とは、両脇の下から腰あたりにある逆三角形の筋肉のことです。背中を覆うほどの大きな筋肉でここを鍛えることで巻き肩を改善できます。広背筋を鍛えられるトレーニングは以下のとおりです。
- うつ伏せになる
- つま先を立てて背中をまっすぐにする
- 両腕が一直線になるように、体から90度の角度で横方向に広げる
- 両腕を伸ばしたまま背中を反らせて上半身を床から離す
- 腕を伸ばしたまま反らした上半身を床に近づける
- 4~5の動作を10回3セットを目安に行う
胸筋を鍛えるトレーニング
胸筋を鍛えることも、巻き肩の改善につながります。胸筋を鍛えるトレーニングの手順は以下のとおりです。
- 腕立て伏せをする体勢になる
- 1の状態から両膝を付ける
- 両手を肩幅より広げる
- 手のひらを外側に向ける
- その状態をキープしたまま、胸を床に近づけるように肘を曲げる
- 床に胸が付くぎりぎりまで体を下ろす
- ゆっくりと肘を伸ばして元の体勢に戻す
- 5~6を10回3セットを目安に行う
正しい座り方を意識する
巻き肩を改善するには、正しい座り方を意識することも大切です。仕事や勉強などで長時間座り続けていると巻き肩になりやすいため、正しい座り方をマスターして美しい姿勢をキープするようにしましょう。正しい座り方のポイントは以下のとおりです。
- 椅子に浅く腰かける
- 背筋を伸ばす
- 骨盤を立てるように座る
座ったときに膝と肘が90度となるように、椅子や机の高さを調整しましょう。正しい姿勢をキープしやすくなります。
専用のアイテムを使用する
巻き肩を改善するためには、専用のアイテムを使用するのも一つの方法です。おすすめのアイテムを使った改善方法は以下のとおりです。
- バランスボールを使う
- 矯正サポーターを着用する
それぞれの改善方法を詳しくみていきましょう。
バランスボールを使う
巻き肩を改善するためには、バランスボールを活用するのがおすすめです。バランスボールに座ると、体がバランスを取ろうとして自然と正しい姿勢をキープできます。座るだけでよいので、テレビを見たり音楽を聞いたりしている時間を有効活用できるでしょう。仕事が忙しくてあまり時間を確保できない方は、朝晩それぞれ5分ずつ座るだけでも効果的です。短い時間でもバランスボールに座る習慣を付けてみてください。
矯正サポーターを着用する
正しい姿勢をキープするためには、矯正サポーターを使用するのもよいでしょう。矯正サポーターを着用すると、猫背の人でも正しい姿勢を維持できます。パソコンを長時間使用するときや勉強をするときなど、正しい姿勢を意識できない場合に活用するのがおすすめです。
ただし矯正サポーターの長時間の着用は避けてください。常に身に着けていると矯正サポーターが当たり前になってしまい、筋肉が衰えてしまうためです。筋力が低下すると巻き肩や猫背を改善できなくなり、状態が悪化する恐れもあります。矯正サポーターはあくまで巻き肩の改善を補助するアイテムとして適度に活用してみてください。
なるべく早く巻き肩を治したいなら肩ボトックス(肩凝りボトックス)がおすすめ
なるべく早く巻き肩を改善したい場合は、肩ボトックス(肩凝りボトックス)の施術を受けるのがおすすめです。今まで紹介した方法は巻き肩を改善できるものの、毎日地道に行って徐々に改善していく必要があります。長く時間を要することから、巻き肩が改善する前に挫折してしまう方もいるでしょう。
一方で、肩ボトックス(肩凝りボトックス)であれば、すぐに巻き肩を改善することが可能です。時間をかけずに美しい姿勢を手に入れられます。
肩ボトックス(肩凝りボトックス)とは?
肩ボトックス(肩凝りボトックス)とは、ボツリヌス菌が作るタンパク質の一種であるボツリヌストキシンを注射することによって肩凝りを緩和させる施術のことです。長時間のデスクワークや勉強をしている人は、姿勢の悪さや巻き肩が原因となり、首から背中に広がる僧帽筋(そうぼうきん)がしこりのように硬くなりやすいです。
僧帽筋に肩ボトックス(肩凝りボトックス)を注入すると、硬くなった筋肉を緩められます。
なお、肩ボトックス(肩凝りボトックス)は注射で製剤を注入するだけの施術であるため体への負担を極力抑えながら、気になる悩みを解決できるでしょう。
肩ボトックス(肩凝りボトックス)の効果
肩ボトックス(肩凝りボトックス)で得られる効果は、主に以下のとおりです。
- 巻き肩の解消
- 肩や首のこりの改善
- 頭痛の緩和
- 首から肩にかけてのラインをすっきりとさせる
- 小顔効果
肩ボトックス(肩凝りボトックス)は巻き肩や肩凝りが改善するだけではなく、肩や首周りがすっきりとするので小顔に見える効果もあります。
肩ボトックス(肩凝りボトックス)の効果の持続期間
肩ボトックス(肩凝りボトックス)は、施術を受けてから1週間程度で効果を実感できるケースが多いです。また筋肉の大きさや肩凝りの度合いによっても異なりますが、1度施術を受けると一般的には4〜5カ月程度は効果が継続します。
効果が薄れてきたタイミングで、再度肩ボトックス(肩凝りボトックス)を受けるのがおすすめです。繰り返し施術を受けることで、継続的に効果を感じられるでしょう。
なお個人差があるものの、2年ほど肩ボトックス(肩凝りボトックス)の施術を受け続けていると筋肉自体が収縮しなくなり、肩凝りを感じにくくなるといわれています。巻き肩になる可能性も低くなるでしょう。また肩ボトックス(肩凝りボトックス)を続けていると、施術の間隔を長くすることも可能です。施術を受ける方によっても異なるので、適切な施術間隔を知りたい場合は医師に確認してみてください。
肩ボトックス(肩凝りボトックス)のデメリット・注意点
肩ボトックス(肩凝りボトックス)のデメリットや注意点は主に以下のとおりです。
- 施術時にチクっとした痛みを感じる
- 軽度なダウンタイムがある
- クリニックによって費用が異なる
- 注入量や注入する箇所を間違えると効果を実感できないケースがある
それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
施術時にチクっとした痛みを感じる
肩ボトックス(肩凝りボトックス)は注射による施術のため、施術時にはチクっとした痛みを感じます。ただし我慢できる程度の痛みであることが多いため、大きな心配は必要ないでしょう。クリニックによっては施術時の痛みを緩和するために麻酔を使用したり、患部を冷やしたりするケースもあります。痛みが気になるようであれば、事前のカウンセリングで相談しておきましょう。
軽度なダウンタイムがある
肩ボトックス(肩凝りボトックス)のダウンタイムは非常に短く、現れる症状も軽度なものがほとんどです。ダウンタイムとして現れる症状は主に以下のとおりです。
- 点状の内出血(コンシーラーやファンデーションでカバーできる程度の症状)
- 患部の腫れ
- 筋肉痛のような倦怠感や痛み
これらの症状が現れたとしても、1〜2週間程度で収まるケースが多いでしょう。ただし肩ボトックス(肩凝りボトックス)は医薬品であるため、ごくまれにアレルギー反応が起きる可能性もゼロではありません。もし体の異変を感じたら、速やかに医師の診察を受けてください。
クリニックによって費用が異なる
肩ボトックス(肩凝りボトックス)は保険適用外の自由診療であるため、クリニックによって費用は異なります。また肩ボトックス(肩凝りボトックス)の効果を維持したい場合、数カ月に1回施術を受ける必要があり、定期的な支出が予想されます。そのため事前に予算内に収まるかを確認しておき、無理のない範囲で施術を受けるようにしてください。
注入量や注入する箇所を間違えると効果を実感できないケースもある
肩ボトックス(肩凝りボトックス)は注入量や注入箇所を間違えると、効果を実感できないケースがあります。満足のいく施術を受けるには、事前のカウンセリングで自分の状態や希望をしっかりと伝えておくことが大切です。また施術を受けるクリニックを選ぶ際にはカウンセリングを丁寧に行ってくれるかどうかを確認しましょう。
共立美容外科の肩ボトックス(肩凝りボトックス)
共立美容外科では、肩ボトックス(肩凝りボトックス)の施術を提供しており、施術前のカウンセリング段階から医師が直接担当します。施術を受ける箇所の状態の確認はもちろん、巻き肩や肩凝りの原因となっているライフスタイルなどについてもしっかりとヒアリングを行います。
また施術では医師が圧痛点やこわばっている部分を触診して注射をする位置を定め、患部の状況に合わせて片側5〜10カ所に注射をします。施術時間は5〜10分と非常に短いため、まとまった時間をなかなか確保できない方でも気軽に施術を受けられるでしょう。
▼共立美容外科で人気の肩こりボトックスの料金や手術方法についての詳細はこちら
厚生労働省やFDAの認可を得た製剤を使用
肩ボトックス(肩凝りボトックス)で使用するボツリヌストキシン製剤にはさまざまな種類がありますが、共立美容外科では以下の2種類を採用しています。
- ボトックスビスタ®:日本の厚生労働省やアメリカのFDA(日本の厚生労働省にあたる機関)から認可を受けている製剤
- ディスポート:アメリカのFDAからの認可を受けている製剤
またボツリヌストキシン製剤は熱に弱いことから、共立美容外科では徹底した品質管理も行っています。
痛みに配慮した施術
先ほども紹介したとおり、肩ボトックス(肩凝りボトックス)は施術時に注射をするので、チクっとした痛みを伴います。そのため共立美容外科では痛みに配慮した施術を行っているのが特長です。
例えば、肩ボトックス(肩凝りボトックス)に使用する注射には細い針を選んでいます。また痛みに不安がある場合には、麻酔クリームや麻酔テープの使用も可能です。別途、料金は必要となるものの痛みを抑えながら施術を受けられるでしょう。痛みが気になる方は、事前に相談するようにしてください。
巻き肩でお悩みの方は共立美容外科へご相談ください
巻き肩とは、肩が内側に入り込んだ状態のことです。両腕が体の前方に入り込んでしまうため見た目が悪くなるだけでなく、さまざまな不調の原因にもなります。そのため巻き肩は早期に改善することが大切です。
巻き肩は自分でストレッチやトレーニングなどを行うことでも改善できるものの、毎日コツコツと地道に実践していかなければなりません。長期的な対策が必要であるため、成果が現れる前に挫折してしまう方もいるでしょう。すぐにでも巻き肩を改善したい方には、肩ボトックス(肩凝りボトックス)の施術がおすすめです。肩ボトックス(肩凝りボトックス)であれば施術から1週間程度で効果を感じられるでしょう。
なお、共立美容外科では十分なカウンセリングを行った上で施術を実施しています。施術を受ける方の肩の状態に合わせて適切な箇所に製剤を注入し、痛みに不安がある場合には麻酔クリームなどの使用も可能です。巻き肩で悩んでいる方や肩ボトックス(肩凝りボトックス)が気になる方は、まずは無料カウンセリングでお気軽にご相談ください。
このページの監修・執筆医師
-
磯野 智崇(いその ともたか)
共立美容グループ 総括副院長
-
略歴
-
- 1995年
- 聖マリアンナ医科大学 卒業
- 1995年
- 聖マリアンナ医科大学形成外科 入局
- 1999年
- 東大宮総合病院整形・形成外科 入職
- 2002年
- 共立美容外科 入職
- 2009年
- 共立美容外科 浜松院院長就任
- 2020年
- 共立美容グループ 総括副院長就任
-
-
主な加盟団体
日本美容外科学会
日本美容外科学会認定専門医
-
SEARCHどのような美容整形をお探しですか?
- お顔の
美容整形 - ボディの
美容整形 - お肌の
美容整形 - その他の
美容整形
×
新宿・名古屋・大阪・福岡をはじめ
全国26院 共通ダイヤル
0120-500-340
あの久次米総括院長も診察♪
新宿本院 直通ダイヤル
0120-500-340
銀座院 直通ダイヤル
0120-560-340
渋谷院 直通ダイヤル
0120-340-428
池袋院 直通ダイヤル
0120-340-800
立川院 直通ダイヤル
0120-489-340
上野御徒町院 直通ダイヤル
0120-340-444