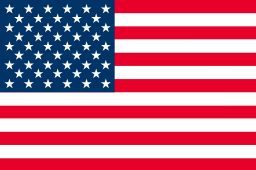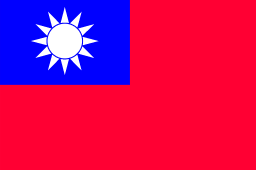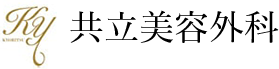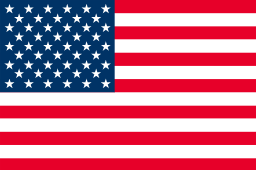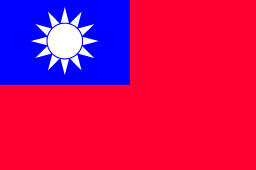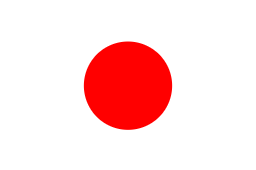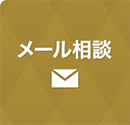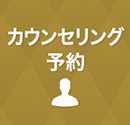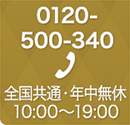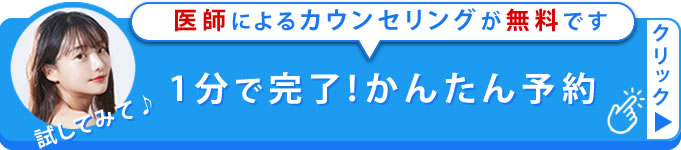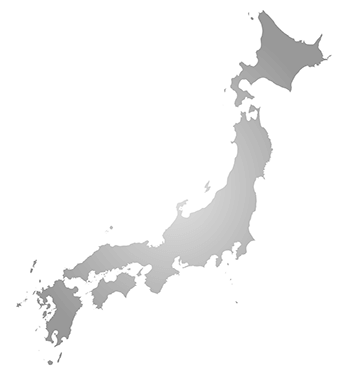日本美容外科医師会認定医院 | 相談・施術の流れ|美容整形・美容外科なら共立美容外科・歯科 ドクターひとりひとりが日々、技術の向上に努力しています。
Kyoritsu Biyo Scrap(KBS)
歯周病を引き起こす3つの原因と対策法
公開日:2022年07月08日(金)
美容歯科

このコラムを読むのに必要な時間は約 9 分です。
最後まで有意義なページになっていますので是非ご覧ください。
目次
歯周病は自覚症状がないまま進行して、最終的には歯を失ってしまう感染症による病気です。
30代後半になると約70%以上の人が歯周病になりますので、早めの対策が必要になります。
そこで今回のコラムでは、歯周病を引き起こす3つの原因と対策法をご紹介しましょう。
歯周病とはどんな症状?
「歯周病」とは歯と歯茎の間にある歯周ポケットに歯垢(プラーク)内の歯周病細菌が入り込んで、歯周組織に炎症を起こす感染症による歯の病気のことをいいます。
歯茎の炎症だけ見られる場合は「歯肉炎」といい、歯茎が赤くなって腫れる症状が見られますが、丁寧にブラッシングすることで歯茎を引き締めて、健康的なピンク色に戻すことが可能です。
「歯肉炎」の症状が進行すると「歯周炎」となり、歯の周りにある歯根膜や歯を支えている歯槽骨・セメント質まで炎症が広がってしまうので、歯周組織が破壊されてしまいます。
これらの症状を総称して「歯周病」と呼びます。歯周病の症状は口内環境の状態によって徐々に進んでいき、軽度・中度・重度のレベルに段階的に進行していきます。
歯周病は自覚症状がない
歯周病は虫歯のように痛みや腫れたりすることがなく、自覚症状がなく静かに進行していきますので「サイレント・キラー(The Silent Killer)」と表現されているほどです。
初期段階では歯磨きの際に歯茎から出血が出たり、歯茎の腫れに気がつくことがありますが、放っておくと次第に歯がグラつくようになり、食事でものを噛むことも難しくなります。
歯周病の重度になると歯が抜けてしまったり、歯周病細菌が口から血管を通って他の臓器に運ばれて、心筋梗塞や脳梗塞など全身の疾患にも悪影響を及ぼすので早めの対策が必要です。
歯周病は治るの?
「歯周病は不治の病」と言われていたのは昔の話し。現代では医学の進歩により、歯周病の研究が進んでおり、症状の進行を阻止することが可能です。
歯周病になっても、症状がそれ以上進行しないようにセルフケアで予防をして、定期的に歯科医院で診断や治療を受けてメンテナンスをすれば、健康な口内環境を維持できるでしょう。
歯周病になる直接的な原因は「歯垢(プラーク)」だと分かっていますので、日頃から口内環境を清潔な状態にするために、セルフケアを怠らないことが基本です。
歯科医院での治療では歯磨きでは取れない歯石を完全に取り除いて、炎症を引き起こす歯周病細菌を除去してくれますので、半年に一度は専門的なクリーニングを受けましょう。
歯周病になる直接的な原因
歯周病になる直接的な原因はお口の中にある歯垢(プラーク)です。
歯垢は約300〜700種類もの細菌が増殖して、生きたまま塊となり、歯と歯茎の間にある歯周ポケットに入り込みます。
ブラッシングによって歯垢が十分に取り切れないと歯の周りにこびりつき、歯垢の中の細菌が毒素を出すようになって歯茎が炎症します。
歯垢はしっかりと取り除かないと石灰化してやがて硬い歯石に変化して、歯の表面に頑固に付着して、毒素や酸素を放出し、歯周組織まで広がって破壊していくのです。
歯石は自分でブラッシングをしても取ることはできませんので、定期的に歯科医院でプラークを除去してもらう必要があります。
歯周病の症状が進行すると最後には歯を支えている骨まで破壊されてしまい、最終的に歯と周りの歯までも抜けてしまう結果になるので、症状の進行を抑えることが重要です。
歯周病を引き起こす3つの原因(リスクファクター)
歯周病を引き起こす直接的な原因は歯垢(プラーク)だと分かりましたが、歯垢が増えてしまうリスクファクターはなんでしょうか。
リスクファクターは大きく分けて、口内環境が悪化していること、喫煙や過度なストレスなど生活習慣、そして糖尿病や女性ホルモンなどの身体的な影響の3つが挙げられます。
では、詳しくみていきましょう。
1)口内環境の悪化
普段から歯磨きやマウスウォッシュをしてセルフケアを頑張っていても、歯垢が残ってしまっている状態であれば、歯周病を引き起こす原因となります。
口内に歯周病細菌を含む多くの細菌が増殖して、歯垢という塊になると、約3日くらいで歯垢は硬い歯石となって歯の表面にガッチリとこびり付いてしまうので注意。
つまり、プラークコントロールがきちんとできていないと歯石の表面に細菌が棲み着いて、歯周病の症状が進行する原因となります。
歯並びが良くない場合は磨きにくい部分に歯垢が増殖させたり、歯科治療で歯に合わない被せもの(クラウン)がある場合も歯垢が付きやすくなるので注意しましょう。
その他には、歯ぎしりや食いしばりのクセがある方も歯ぐきに強い力がかかって炎症が起こりやすく、歯周病のリスクファクターとなり得るので早めに治療が必要になります。
口呼吸のクセがある方、口をぽかんと開けるクセがある方も口内が乾燥しやすく、プラークが付きやすいので、歯周病予防のためにも改善することが大切です。
2)喫煙やストレスなどの生活習慣
口内環境に歯垢が増えてしまう原因は喫煙習慣や過度なストレスを受けたり、生活習慣による影響も大きいです。
特に喫煙者は歯周病になりやすく、進行も速くなるので要注意です。
タバコを吸うと血管が収縮して歯茎の血行が悪くなりますので、十分な栄養や酸素が行き渡らず、歯周病への抵抗力が弱くなります。
その結果、プラークが付きやすくなります。
食生活はビタミンやミネラルなど栄養バランスが取れていることが理想です。
栄養不足や柔らかいものばかり食べていると、歯周組織の抵抗力を弱め、歯垢が増える原因となります。
また、仕事や日常生活でストレスを溜め込んでいると、精神的なダメージから体の抵抗力が弱くなり、歯周病が悪化しやすい状態になるので注意が必要です。
自分なりにストレス発散法を見つけて、歯周病対策のためにもリラックスする時間を摂るようにしましょう。
3)糖尿病など生活習慣病
糖尿病の方は全身の免疫力が低下するので、歯周病のリスクが2倍以上高くなるという調査結果が報告されており、歯周病を進行させるリスクファクターとなります。
高血糖になると唾液の分泌量が減り、口の中が乾いて歯周病菌が増殖しやすい環境になるので、糖尿病の方はより入念にセルフケアをすることが大切です。
その他には、心疾患や脳血管疾患、ホルモン異常など全身疾患がある方、降圧剤、てんかん)剤、免疫抑制剤などの薬を長期服用されている方も歯周病リスクは増加します。
歯周病は進行型!3つの段階で進みます
歯周病とは歯と歯茎が炎症する総称のことをいい、進行過程によって3つの段階があります。
健康な歯茎の状態は歯と歯肉の境は1~2mm程度の溝があり、薄いピンク色をしていて弾力があり引き締まっていて、歯磨きをしても出血はありません。
▽軽度の歯周病の症状
- 歯周ポケット 2mm〜5mm
- 歯茎が赤くなる
- 歯茎が炎症してプクッと腫れる
- 歯磨きをすると歯茎から出血する
- 口臭が気になる
- 歯が浮いた感じがする
- 歯がムズムズかゆい感じがする
▽中度の歯周病の症状
- 歯周ポケット 5mm〜7mm
- 歯茎が腫れて痛い
- 歯のグラつきがある
- 硬い食べ物が噛みにくい
- 歯茎が下がって歯が長くなった
- 歯茎を触ると膿が出ることがある
- 強い口臭がある
▽重度の歯周病の症状
- 歯周ポケット 7mm以上
- 物を噛めないほど歯のグラつきがある
- 歯茎がブヨブヨで血や膿が出る
- 口臭がかなり強い
- 朝目覚めると口の中がネバネバし、血の味がする
歯茎の炎症だけ見られる場合は、「歯肉炎」といいブラッシングなどで歯茎を引き締めれば改善の余地が十分にあります。
歯茎の炎症が歯槽骨や歯根膜にまで広がると「歯周炎」となり、軽度・中度・重度と症状が進んでいき、歯槽骨が半分以上溶けると歯はグラついて、最終的には歯が抜けてしまうのです。
歯周病の進行を防ぐ3つの対策法
歯周病予防は、口内にプラークを増やさないことがカギです!
口腔内の歯周病菌を減らすことができれば、歯周病の進行を抑えることができます。
ここからは、歯周病の進行を阻止するための3つの対策法をみていきましょう。
難しいことはなく、ちょっとした心がけで口内環境を清潔に保つことができます。
1)セルフケアを見直す
歯磨きを基本とするセルフケアを怠っていると歯周病の症状が進行しますので、この機会にセルフケアを見直して、丁寧なブラッシングと口腔ケアを取り入れていきましょう。
歯磨きは歯と歯茎の間に歯ブラシを斜め45度の角度に置いて、小刻みに1センチずつ動かしながら、歯垢(プラーク)を取り除くイメージで、隅々まで丁寧にブラッシングします。
歯茎から出血したり、歯茎がブヨブヨしている状態の方は歯周病菌が毒素を出して炎症を起こしていることが原因です。
歯磨き粉は歯肉炎・歯周炎予防の効果が期待できる薬用歯磨き粉、歯磨きの後は細菌の増殖を抑える殺菌作用があるデンタルリンスを併用すると良いでしょう。
磨き残しがあると、残った歯垢(プラーク)が石灰化して歯石に変化して、歯の表面にこびり付いて歯周病を進行させる原因となるので注意が必要です。
2)歯科医院で治療を受ける
歯周病の症状は進行しますので、半年に一回のペースで歯科医院の定期健診を受けて、お口の状態をチェックしてもらいましょう。
歯にこびり付いた歯石は自分でブラッシングしても取ることはできませんが、歯科医師や歯科衛生士など歯科の専門家によるクリーニングで歯石はキレイに取り除いてもらえます。
歯周炎まで進行している中度・重度の場合は、歯肉を切開して歯石を除去する歯周外科治療、もしくは歯周組織を再生させる歯周組織再生療法が行われる場合もあります。
歯周病の治療後も自宅でのセルフケアを忘れずに定期的に定期健診を受けて、メンテナンスをすることが大切です。
3)生活習慣を見直す
歯周病は生活習慣病として位置づけられており、日頃からストレスを溜め込まず、適度な運動と十分な睡眠を取り、栄養バランスの良い食生活を心がけることが大切です。
歯周組織の抵抗力を強めるために、食品からビタミンA,Cタンパク質、カルシウム、鉄分などをバランス良く摂取していきましょう。
タバコを吸う習慣がある方は歯周病の他、様々な生活習慣病のリスクファクターになりますので、健康的なリラックス法に切り替えることで、歯周病の進行を抑えることができます。
歯周病を改善して自信溢れる笑顔に!共立美容外科・歯科におまかせください
「共立美容外科・歯科」は美容外科が美しさを追求した様々な歯科治療を提供しております。
歯科の審美歯科部門は症状を改善する目的のほか、仕上がりの美しさを重要視しておりますので、患者様の笑顔をより一層輝くお手伝いに力を入れています。
歯周病治療の他、矯正、インプラント、ホワイトニング、入れ歯、歯茎の見た目の改善など豊富な治療メニューが揃います。気になる方は、当院へお気軽にお問い合わせください。
▼共立美容外科の人気のインプラント治療にの料金や手術方法の詳細はこちら
このページの監修・執筆医師
-
諸岡 梨沙(もろおか りさ)
日本アンチエイジング歯科学会認定医
メディカルアロマセラピスト認定医-
略歴
-
- 2005年
- 福岡歯科大学 卒業
- 2009年
- 共立美容外科・歯科 入職
- 2009年
- 共立美容外科・歯科 大阪本院(歯科部門)院長就任
-
-
主な加盟団体
日本口腔インプラント学会
日本審美歯科学会
日本補綴歯科学会
顎機能咬合学会
アンチエイジング歯科学会
アンチエイジング歯科学会認定医
メディカルアロマセラピスト認定医
ヨガインストラクター
-
SEARCHどのような美容整形をお探しですか?
- お顔の
美容整形 - ボディの
美容整形 - お肌の
美容整形 - その他の
美容整形
×
新宿・名古屋・大阪・福岡をはじめ
全国26院 共通ダイヤル
0120-500-340
あの久次米総括院長も診察♪
新宿本院 直通ダイヤル
0120-500-340
銀座院 直通ダイヤル
0120-560-340
渋谷院 直通ダイヤル
0120-340-428
池袋院 直通ダイヤル
0120-340-800
立川院 直通ダイヤル
0120-489-340
上野御徒町院 直通ダイヤル
0120-340-444