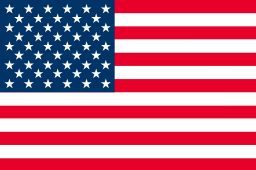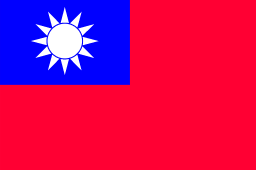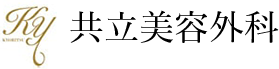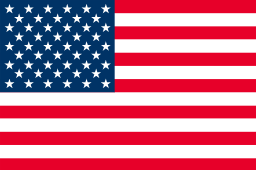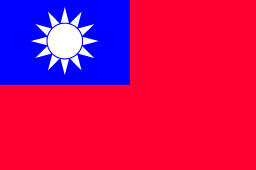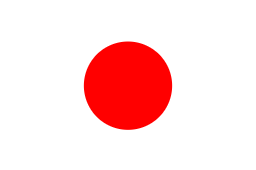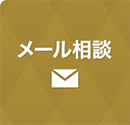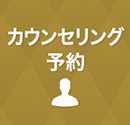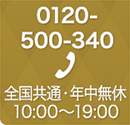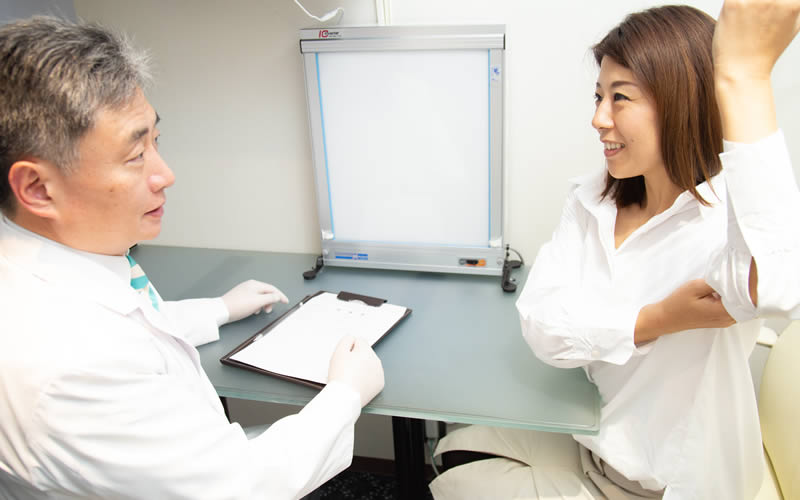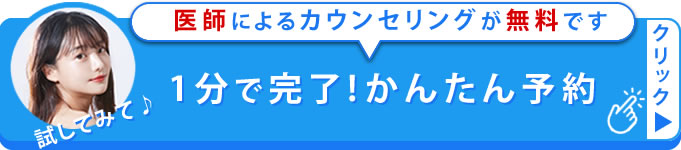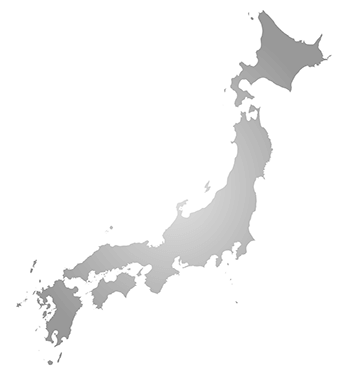日本美容外科医師会認定医院 | 相談・施術の流れ|美容整形・美容外科なら共立美容外科・歯科 ドクターひとりひとりが日々、技術の向上に努力しています。
Kyoritsu Biyo Scrap(KBS)
汗の臭い対策に制汗剤は使わない方がよい?制汗剤にまつわるうわさの真相を徹底解説
公開日:2024年01月14日(日)
わきが・多汗症

このコラムを読むのに必要な時間は約 16 分です。
最後まで有意義なページになっていますので是非ご覧ください。
目次
汗の臭い対策に、制汗剤を使用している方は多いでしょう。しかし制汗剤にまつわるさまざまなうわさが出回っており「使わない方がよいのだろうか」と不安に思う声も聞かれます。
本記事では、制汗剤にまつわるうわさを解説します。制汗剤に期待できる効果や適切な使い方、併せて試したい汗のケア方法なども紹介しているので、参考にしてみてください。
私たちの体にとって汗は止めてもよいもの?
汗の臭いを何とかしたくて、制汗剤をたくさん使ってしまう方もいるでしょう。しかし、汗は本当に止めてもよいものなのでしょうか。ここでは、汗の役割と臭いの原因を理解していきましょう。
汗の役割
汗の主な役割は体温調整です。体は、汗の水分が皮膚の上で蒸発するときの気化熱を利用して、体温を下げています。もし汗が出ずに高温状態が続いてしまうと熱中症などの体調不良になり、健康な状態を維持できません。つまり汗は、人が生きていく上で欠かせない働きを担っています。
なお、汗はエクリン汗腺とアポクリン汗腺と呼ばれる2種類の汗腺で作られている物質です。エクリン汗腺は全身に分布しており、主に体温を下げたり皮膚の乾燥を防いだりするために汗を分泌しています。アポクリン汗腺は脇の下や耳の穴などに存在していて、フェロモンを出す役割を持つ汗を出しています。
汗の臭いの原因
汗が体にとって大切な働きがあると理解できても、臭いが気になってしまう方は多いでしょう。しかし汗は基本的に無臭であり、臭いの原因となる物質はほとんど含まれていません。なぜなら汗の原料は、血液から赤血球などを取り除いた血漿(けっしょう)だからです。
汗は、皮膚の表面に存在している皮脂や常在菌などと混ざることで細菌分解が行われて、嫌な臭いを発生しています。つまり汗の臭いは汗自体から発せられているのではなく、出た後の皮膚の状態によって左右されます。
制汗剤に期待できる効果
汗の臭いを抑えるアイテムとして人気の高い制汗剤には、以下のような効果が期待できます。
- 汗の抑制
- 殺菌
- 消臭
制汗剤の中には、汗の出口を小さくして発汗を抑える役割を持つ収れん作用が含まれています。この成分が入っていると汗自体を抑制できるため、気になる臭いを抑えやすくなります。また殺菌成分や臭いを吸着する消臭成分なども入っており、汗が細菌分解されにくい環境を整えてくれるでしょう。つまり制汗剤を使用すると直接汗を抑制できないものの、気になる臭いをカバーできます。そのため日常的にうまく活用することで、汗の臭いが気になりにくくなります。
「制汗剤は使わない方がよい」といううわさは本当?
先述のとおり制汗剤には汗の臭いを抑える役割があるものの「あまり制汗剤は使わない方が良い」とのうわさがあるのも事実です。実際は正しい使い方を守れば問題ないのですが、なぜこのようなうわさが出るのでしょうか。
ここでは、以下のような制汗剤にまつわるうわさについて解説します。
- わきがになる
- 体臭が強くなる
- 体に害がある
- 肌が荒れる
それぞれのうわさの真偽を明らかにしていきましょう。
うわさ①わきがになる
制汗剤を正しく使用していれば、わきがになることはありません。そもそもわきがとは、脇の下にあるアポクリン汗腺から分泌される汗で起こる嫌な臭いのことです。アポクリン汗腺の数が多いと、わきがになりやすいといわれています。
そしてわきがを発症する主な要因は遺伝や性ホルモンの乱れ、不摂生な生活習慣などです。男性だけではなく、女性でも起こり得るため日頃から臭いをチェックしておきましょう。
なお、制汗剤の使い方を誤るとわきがのように臭いがきつくなるケースがあります。例えば制汗剤を使いすぎると皮膚の乾燥を招き、過剰に皮脂を分泌します。すると汗が出たときに皮脂と反応して、強い臭いを発することもあるのです。
さらに制汗剤によって毛穴が塞がれたままになると細菌が繁殖しやすくなるため、嫌な臭いが起こりやすくなるでしょう。そのため制汗剤は適度な使用に留めて、脇をきれいに保つことが大切です。
うわさ②体臭が強くなる
制汗剤を適切に使用していると、体臭が強くなることはありません。そもそも制汗剤は発汗を抑えるために使用するので、外出前に使うと汗や臭いを抑制できます。しかし、誤って汗をかいた後に使うと十分な抑制効果を得られないだけではなく、制汗剤の香りと汗の臭いが混ざってさらに臭いがきつくなるケースもあります。その結果、体臭が強くなったと勘違いする方もいるでしょう。
制汗剤は正しく使うことで汗を抑えられ、嫌な臭いが出にくくなります。なお制汗剤を使用したからといって、もともとあるわきがの症状が悪化することもありません。臭いがきつくなったと感じたのであれば、他に要因が隠れていると考えられます。
うわさ③体に害がある
制汗剤を適切に使用していれば、体に害が出ることは考えにくいです。ただし先述のとおり制汗剤は発汗を抑えるアイテムであるため、使いすぎると制汗剤に含まれる塩化アルミニウムと皮膚の角層が結合して毛穴を塞ぐことがあります。
すると汗腺から汗が出にくくなり、うまく体温調整できなくなる可能性があるでしょう。正常な体温をキープできないと熱中症などのリスクが懸念されるため、体に悪影響を及ぼすかもしれません。
また殺菌や除菌効果のある制汗剤を多用すると常在菌のバランスが崩れやすくなるため、免疫力の低下を引き起こす可能性もあります。その結果、体に害があると思う方もいるでしょう。そのため制汗剤は全身に使用するのではなく、脇や足などの一部分に留めておくのがポイントです。
うわさ④肌が荒れる
制汗剤を適切に使用していると、肌が荒れる可能性は低いです。しかし制汗剤にはさまざまな成分が含まれているため、局所的に接触皮膚炎(かぶれ)やかゆみを起こす可能性があります。多くの制汗剤に含まれている塩化アルミニウムは、多汗症治療薬としても使用されている成分ではあるものの、皮膚刺激によるかぶれやヒリヒリ感などが起きやすいのが特徴です。特に肌の弱い方は反応しやすいため、使用の際には注意が必要です。
かぶれが続くと炎症後の色素沈着を引き起こす可能性があります。皮膚に異常を感じたらすぐに制汗剤の使用を中止して、皮膚科を受診することをおすすめします。
制汗剤の適切な使い方
制汗剤は医薬部外品の腋臭防止剤に分類され、体臭の防止を目的とした外用剤です。先述のような間違った使い方によるリスクを避けるためにも、あらかじめ制汗剤の正しい使い方を理解しておくことが大切です。
ここからは制汗剤の種類と使い分け、使用するタイミングについて解説します。
制汗剤の種類と使い分け
制汗剤の種類や特徴は以下の表のとおりです。
| 制汗剤の種類 | 特徴 | おすすめの部位 |
| スプレー |
|
全身(特に背中) |
| ロールオン |
|
脇 |
| シート |
|
全身 |
| スティック |
|
脇 |
| ウォーター |
|
全身 |
種類によっては、汗をかいた後に使用できる制汗剤もあります。そのため「どのような場面で使用したいか」などを考慮しながら、自分に合った制汗剤を選ぶとよいでしょう。
使用するタイミング
制汗剤の効果を高めるためには、起床後にシャワーを浴びてから使用するのがおすすめです。すると寝ている間にかいた汗が流れて、きれいな肌の上から制汗剤を使用できます。
また汗をかいた後に使用したい場合は、一度濡れたタオルや汗拭きシートで汗をぬぐってから制汗剤を活用するのがポイントです。濡れたタオルで汗をぬぐうと体の表面に適度な湿り気が残るため、汗の代わりに体を冷やしてくれます。
反対に乾いたタオルでゴシゴシとこすってしまうと気化熱をうまく活用できないため、さらに汗をかいてしまうでしょう。汗拭きシートを併用すれば、汗によるべたつきを解消しながら肌を清潔にできます。
制汗剤の使用と併せて取り入れたい汗の臭いケア
制汗剤の使用と併せて取り入れたい汗の臭いケア方法は以下のとおりです。
- 小まめに汗を拭く
- 食事内容を見直す
- 意識的に汗をかく
それぞれの方法について解説します。
小まめに汗を拭く
臭いを防ぐためには、小まめに汗を拭き取ってください。汗をかいたまま放置していると、皮脂や雑菌と混ざってしまい嫌な臭いを発しやすくなります。汗をかいた後5~10分以内に拭き取り、常に汗がない状態をキープしておきましょう。
もし可能であれば清潔な洋服に着替えるのもおすすめです。リネンやコットンなど通気性が良く、かつ汗を吸収しやすい素材の服に着替えておくと臭いが出にくくなります。
なお臭いは汗が出てきた場所だけではなく、汗を吸収した衣服からも発生します。いくら制汗剤を使用して汗のケアを行っていたとしても、衣服から臭いが出ていたら意味がありません。そのため汗をかいたときは衣服にも注意しておき、清潔な状態を保つことが大切です。
食事内容を見直す
臭いのケアをしたい方は食事内容を見直してみましょう。アポクリン汗腺から分泌されるタンパク質や脂質の量を減らすと、臭いの原因を抑えられます。控えておきたい具体的な食品例は以下のとおりです。
| 食品 | 体臭の原因となる理由 |
| 肉類 |
|
| 動物性脂肪
(牛乳やチーズなど) |
|
| にんにく |
|
| からい食べ物 |
|
| アルコール |
|
なお、以下の食品は汗の臭いを抑える効果が期待できます。体にとっても良い食品であるため、意識的に摂取するようにしましょう。
| 食品の種類 | 具体例 | おすすめのポイント |
| 抗酸化食品
(ビタミンCやEを多く含む食品) |
|
タンパク質や脂質の酸化を抑制できる |
| アルカリ性食品 |
|
体内での乳酸の生成を抑制できる |
| 腸内環境を整える食品 |
|
腸内の善玉菌を増やして、悪玉菌を減らす |
意識的に汗をかく
臭いが気になる方は、意識的に汗をかくようにしましょう。「臭いをなくすためには汗をかかなければいい」と考える方もいるかもしれません。しかし抑制しすぎると汗腺の働きを弱めてしまい、さらなる臭いの原因になります。
また汗をかかないようにするために、水分を控えるのもおすすめできません。水分の摂取量が減ると臭い成分が便として排出されにくくなるため、かえって体臭が悪化する原因になります。そのため運動や入浴などを日常的に行って、汗をかく習慣を身につけておくのがおすすめです。
良い汗が出る入浴方法
手軽に始められる入浴での汗腺トレーニングを紹介します。どちらの方法も簡単に試せるので、気になるトレーニングから挑戦してみてください。
- 手足高温浴
- 浴槽に43~44度ほどのお湯を貯める
- 両肘から先、両膝の下をお湯につける
- 2の状態をキープしたまま10~15分温める
- 半身微温浴
- 浴槽に37~38度ほどのお湯を貯める
- みぞおちあたりまで浸かる
- 10~15分ほど半身浴を行う
日常生活に影響が大きいなら病院に相談しよう
過度な発汗や臭いが原因でストレスを感じたり、日常生活に支障が出たりしている場合は医師の診察を受けましょう。市販の制汗剤はあくまで一時的な効果に留まります。一方、病院であれば飲み薬や外用薬などを使用したり、必要に応じて処置や手術を受けたりできるため汗に関する悩みを解決できます。症状に応じて適切な治療を行ってもらえるため、日々の生活に不安を感じるようであればまずは相談してみるのがおすすめです。
何科を受診すればよい?
汗に関する治療を受けられるのは、主に以下の3つの診療科です。
- 皮膚科
- 形成外科
- 美容外科
皮膚科では、主に医薬品を用いて皮膚の表面から治療をしています。行きつけの皮膚科があれば、そこで対応してもらうとよいでしょう。ただしわきが治療には対応していない皮膚科もあるため、事前に問い合わせておくのが望ましいです。
形成外科では皮膚の表面上で行う治療よりも、手術をはじめとする外科的治療に力を入れて対応しています。そのため服薬や塗り薬では効果が得られない場合は、形成外科を受診するのも一つの方法です。
美容外科は疾患ではないものの、美容を目的として処置を行う診療科です。外科的な処置がメインとなるため、原因に対して根本的なアプローチが可能です。それぞれの特徴を理解した上で診療科を選びましょう。
幅広い施術から選ぶなら美容外科がおすすめ
制汗剤を使用した日常的なケアに限界を感じている場合は、汗腺の働きを抑えたり汗腺自体を除去したりするのも一つの方法です。美容外科であれば、さまざまな施術の中から自身の要望に応じた方法を選択できます。
なお、汗腺を除去すると「体温調整に支障が出るのではないか」「体に何らかの害が出るのではないか」などと不安に思う方もいるかもしれません。しかし人体には400万もの汗腺があり、脇の下にあるのはそのうちの約2%だといわれています。この2%を除去しても体の機能に影響を及ぼすことは考えにくいため、施術後も問題なく体温調整などを行えます。そのため汗に関する悩みを抱えている方は、汗腺の除去や抑制などを検討してみてもよいでしょう。
共立美容外科の代表的な汗を抑える治療
共立美容外科で行っている代表的な汗を抑える施術方法は以下のとおりです。
- 超音波+ローラークランプ法
- ベイザー+ローラークランプ法(大阪本院・仙台院限定)
- ミラドライ
- ボトックス注射
それぞれの施術方法について詳しく解説します。
超音波+ローラークランプ法
超音波+ローラークランプ法とは、アポクリン汗腺やエクリン汗腺を除去する施術のことです。脇を大きく切開する従来のわきが手術・多汗症治療では、術後のケアが大変だったり汗腺がほとんど取れなかったりしました。しかし超音波+ローラークランプ法はこれらの欠点を改良した独自開発の施術方法です。超音波をかけた後にローラークランプを用いて汗腺を吸引し、汗や臭いの元を除去します。
超音波+ローラークランプ法では2~4mmほどの超極細カニューレ(吸引棒)を使用して、汗腺を吸引します。もともと傷口は小さいものの、万が一でも跡が残らないようにするために傷跡を保護するKBシースという器具も併用しているのが特長です。
施術の際は痛みに配慮しているため、痛みに敏感な方でも安心して施術を受けられます。極細の注射針を使用してゆっくりと麻酔液を注入しているため、ほとんど痛みを感じないでしょう。共立美容グループには日本麻酔科学会の専門医などが在籍しており、施術に適した麻酔を日々研究しています。また痛みに弱い方には笑気麻酔やエクスパレス麻酔(施術後72時間痛みを緩和できる麻酔)を利用することも可能です。カウンセリング時にお問い合わせください。
なお超音波+ローラークランプ法は、小学生から受けられます。未成年者の場合は、将来性も考えて傷跡に配慮した施術を行います。
具体的な施術の流れは以下のとおりです。
- 担当医師によるカウンセリングを受ける
- 見積もりを確認する
- 問題がなければ手術室へ移動する
- 麻酔クリームを塗布する
- 麻酔が効くまで30分ほど待つ
- 麻酔クリームを拭き取る
- 超音波を当てる
- 脇の消毒を行う
- 汗腺を除去する部分に印をつける
- 麻酔の注射を行う
- 脇に小さな穴を開ける
- 11に傷跡保護器具を装着する
- 麻酔液を注入する
- ローラークランプを使用して汗腺類を吸引する
- 脇を縫合する
- 施術部位を圧迫固定する
- 帰宅する
施術後、1週間を目安に検診を受けてください。アフターケアも充実しているため、気になることがあれば対応いたします。
共立美容外科の人気のローラークランプ法の手術方法や料金についてはこちらから。
ベイザー+ローラークランプ法(大阪本院・仙台院限定)
ベイザー+ローラークランプ法とは、特許を取得したローラークランプ法にベイザーリポ2.0を組み合わせた施術方法です。ベイザーリポ2.0とは、ベイザー波と呼ばれる特殊な領域の超音波振動を出す医療機器のことです。このベイザー波の熱を使用して脂肪細胞を溶かすことで、より効率的に汗腺を吸引します。周辺の血管や組織をなるべく傷つけずに施術を行えるのが特長です。
以前に切開手術などを行って皮膚が硬くなっている場合や重症の方は、ベイザーを用いたこちらの施術方法がおすすめです。どちらの施術方法が適しているか分からない場合は、お気軽にご相談ください。
なお、ベイザー+ローラークランプ法は大阪本院と仙台院のみの限定施術方法です。
▼共立美容外科の「ベイザー+ローラークランプ法」についての詳細はこちら
ミラドライ
ミラドライとは、皮膚を切開することなくわきが手術・多汗症治療を行えるマシンのことです。マイクロ波(電磁波)エネルギーを利用して汗腺の機能を抑制します。失われた機能は再生できないため、外科的手術と同様の効果が期待できます。
ミラドライは皮膚を切っていないため、合併症などが起こりにくいのが特長です。傷跡を心配する必要もなく、片側約20~30分と短い時間で施術を受けられます。術後少し腫れが見られるものの、ダウンタイムが比較的少ないのもうれしいポイントでしょう。運動や入浴は控える必要がありますが、施術当日より日常生活を送れます。
なお、共立美容外科のミラドライは超音波と併用しています。痛みをさらに軽減でき、施術後の腫れを少なくできるからです。その分、料金を高く設定しているということもないため、ぜひ併せて活用してみてください。
▼共立美容外科で人気のミラドライの料金や手術方法についての詳細はこちら
ボトックス注射
ボトックス注射とは、脇の下にボトックスを注射することで汗腺を細くして汗を出にくくする施術方法のことです。1回の施術時間は約10分で、一般的な汗かきの方にも対応しています。
共立美容外科では安全性を重視した製剤を選んでおり、ボトックスビスタもしくはディスポートを使用しています。ボトックスビスタはボツリヌス菌を精製したもので、日本の厚生労働省とアメリカのFDA(日本の厚生労働省にあたる機関)の認可を受けている製剤です。
ディスポートはヨーロッパをはじめ世界23ヵ国で使用されており、こちらもFDAの認可を受けています。なおボトックス注射の効果は半永久的ではないため、半年に1回ほどのペースで施術を受ける必要があります。
▼共立美容外科の人気の脇のボトックスの料金や種類についての詳細はこちら
汗の量や臭いでお悩みの方は共立美容外科へご相談ください
汗は体温調整や保湿効果などの役割があり、人が生きていく上で欠かせない機能です。しかし汗は嫌な臭いの原因ともなり得るため、うまく付き合っていく必要があります。制汗剤をうまく活用したり、小まめに汗を拭いたりして臭いが発生しないように注意することも大切です。
とはいえ日常生活に支障が出るほど汗に困っている場合は、美容外科で施術を受けるのも方法の一つです。幅広い施術方法の中から自分に適したものを選ぶと、悩みや不安を解消しやすくなります。
共立美容外科ではさまざまな施術方法を提供しており、一人ひとりが抱える悩みを解決しています。痛みや傷跡などにも配慮しているため、施術後の生活にも影響が少ないでしょう。汗の量や臭いにお悩みの方は、ぜひお気軽に無料カウンセリングへお越しください。
このページの監修・執筆医師
-
磯野 智崇(いその ともたか)
共立美容グループ 総括副院長
-
略歴
-
- 1995年
- 聖マリアンナ医科大学 卒業
- 1995年
- 聖マリアンナ医科大学形成外科 入局
- 1999年
- 東大宮総合病院整形・形成外科 入職
- 2002年
- 共立美容外科 入職
- 2009年
- 共立美容外科 浜松院院長就任
- 2020年
- 共立美容グループ 総括副院長就任
-
-
主な加盟団体
日本美容外科学会
日本美容外科学会認定専門医
-
SEARCHどのような美容整形をお探しですか?
- お顔の
美容整形 - ボディの
美容整形 - お肌の
美容整形 - その他の
美容整形
×
新宿・名古屋・大阪・福岡をはじめ
全国26院 共通ダイヤル
0120-500-340
あの久次米総括院長も診察♪
新宿本院 直通ダイヤル
0120-500-340
銀座院 直通ダイヤル
0120-560-340
渋谷院 直通ダイヤル
0120-340-428
池袋院 直通ダイヤル
0120-340-800
立川院 直通ダイヤル
0120-489-340
上野御徒町院 直通ダイヤル
0120-340-444